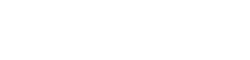この仕事をしていると、従業員、特に若い子たちを指導する場面が毎日のようにあります。正直に言うと、「叱る」ってのはものすごくエネルギーを使います。できれば穏便に済ませたい。でも、工場の安全や製品の品質を守るため、そして何より本人の成長のために、言わなきゃいけないことは言わないといけません。
目的は相手をへこませることじゃなく、成長してもらうこと。だから、単に感情をぶつけて怒鳴り散らすのとはワケが違います。今回は、私が長年の経験から「これだけは絶対にやらない」と決めている、叱るときのマイルールを3つ、お話ししようと思います。
なぜ私が「叱り方」にこだわるのか
そもそも、なぜ叱るのか。それは「問題の再発防止」と「本人の成長」のためです。
感情的に怒鳴ったところで、相手は萎縮して思考停止に陥るだけ。「怒られないようにするにはどうするか」しか考えなくなり、挑戦する気持ちも失せてしまいます。それでは何の意味もありません。
よく言いますが、「怒る」のは自分の感情の発散で、「叱る」のは相手のための指導です。「怒った」後は、自分にも相手にも後味の悪い空気が残るだけですが、うまく「叱れた」ときは、相手の表情に納得の色が見えたりする。この違いは、日々の業務を円滑に進める上で欠かせない「信頼関係」に直結します。だからこそ、私は叱り方にこだわるんです。
私が絶対にしないと決めている3つのこと
では、具体的に私が実践している3つのルールを紹介します。当たり前のことかもしれませんが、常に意識するのは意外と難しいんですよ。
みんなの前で叱らない
これは鉄則中の鉄則ですね。他の従業員が見ている前で叱責するのは、本人からすれば「晒し者」にされているのと同じです。ミスした内容よりも「みんなの前で恥をかかされた」という屈辱感の方が強く心に残り、素直に反省するどころか、反発心を生むだけ。本当に伝えたいことが、ノイズに消されてしまうんです。話をするなら、必ず一対一になれる場所で、落ち着いて。これが大前提です。
過去の話を持ち出し、人格を否定しない
「前にも同じようなミスがあったよな」「だから君は詰めが甘いんだ」
こんなふうに、過去の失敗を蒸し返したり、その人の人格や性格と結びつけたりするのは絶対にNGです。人格を否定する言葉は、相手の逃げ道をなくし、自信を根こそぎ奪ってしまいます。叱るときに焦点を当てるべきは、その人の人格ではなく、あくまで「今回起きた事実(行動)」だけ。「この行動が、こういう問題を引き起こした。だから、次からはこう改善してほしい」と、事実ベースで具体的に伝えることが大切です。
叱りっぱなしで終わらせない
これが一番大事かもしれません。厳しい言葉は、いわば苦い薬。そのまま渡すだけでは、ただただ苦い。だからこそ、叱った後のフォローが重要になります。気まずい空気のまま突き放すのではなく、「期待しているからこそ、厳しく言ったんだぞ」「この失敗を次に活かせば、もっと成長できる」といった一言を添えるようにしています。「君を見捨ててはいないよ」というメッセージを伝えることが、明日からの彼の働く力になると信じています。
もちろん、私だって完璧な上司ではありません。時には感情的になりかけて、ハッと我に返ることもあります。でも、愛情をもって真剣に向き合う姿勢だけは、忘れずにいたい。部下を指導することで、自分自身もまた成長させてもらっている。そう感じながら、明日も現場に立ちたいと思います。